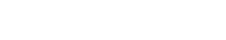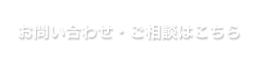スタンフォードd.schoolデザイン思考ブートキャンプ体験記
みなさん、こんにちは!
先週、スタンフォード大学d.schoolのデザインシンキングブートキャンプに参加してきました!とても刺激的な経験で、イノベーションについての考え方が根本から変わりました。その貴重な学びをシェアしたいと思います。
デザインシンキングは単なる手法ではなく、イノベーションの思考法そのものでした。
デザインシンキングって結局何?痛みを理解することでした

このブートキャンプで一番心に残ったのは「顧客の痛みを深く理解する」ことの大切さです。表面的なニーズではなく、本当の痛みポイントを見つけることが全ての始まりなのです。
プロセスは4つのステップで進みました:
- 問題を広げる (Diverge problem)
- 問題を絞る (Converge problem)
- 解決策を広げる (Diverge solution)
- 解決策を絞る (Converge solution)
このダブルダイヤモンドと呼ばれるプロセスが、非常に効果的でした!
発散と収束を繰り返すことで、本質的な問題と革新的な解決策が見えてきます。
「えっ、そんなこと言うの?」から始まるイノベーション

特に興味深かったのは、インタビューした人の「予想外の発言」からアイデアを掘り下げていく手法です。
具体的には:
- 特定の人をピックアップして深掘りインタビュー
- その人の「えっ、そんなことを考えているの?」と驚く発言を見つける
- 「この言葉、本当は何を意味しているのだろう?」と考える
- 「こんな状況があれば、ゲームチェンジできるのでは?」とアイデアを膨らませる
これにより、人の言葉の裏にある本当の意味を考える習慣がつきました。これは、ビジネスでもプライベートでも活用できます!
驚きの瞬間こそが、イノベーションの入り口なのです。
自分の弱点発見:アイデアは出せるけど決められない
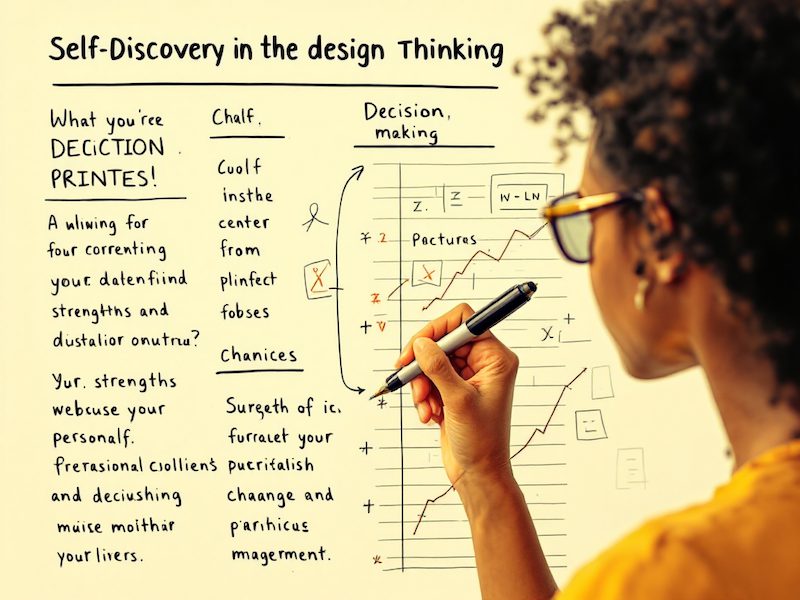
自分自身についても興味深い発見がありました:
- アイデアを出す段階はとても楽しい!
- しかし、それを絞り込む段階になると途端に苦手意識が…
社長でありながら決断が得意ではないというのは、なかなかの矛盾ですね(笑)。ですが、自分の弱みを知ることで、チーム構成の重要性がよく理解できました。
自己認識は、より良いチーム構築への第一歩です。
ダイバーシティって、実は素晴らしかった

他の参加者を見ていて衝撃的だったのは、彼らが遠慮なく意見をぶつけ合うことです。時には他人の付箋を剥がして「いや、こちらの方が適切です」と自分のアイデアを上書きしていきます。
正直、これまで「ダイバーシティ」という言葉に「意識高い系かな…」と距離を置いていましたが、この体験で考えが180度変わりました。多様な考え方や意思決定スタイルを持つ人たちがいるからこそ、イノベーションが生まれるのだと実感しました。
多様性は単なるスローガンではなく、イノベーションの原動力です。
これからどう活用するか?

この学びは、以下のように活かしていきたいと思います:
- 会社のマーケティング戦略を、顧客の本当の痛みから考え直す
- クライアントのマーケティングサポートで、表面的なニーズではなく本質的な課題に焦点を当てる
特にAIなどの新しい技術の話をする時、つい「AIはすごいですよ!」といった技術主導の話になりがちですが、「ユーザーの痛みに寄り添ったAI活用」を考えることの大切さを学びました。
技術そのものより、その技術が解決する「人の痛み」にフォーカスすることが重要です。
結論として
デザインシンキングの本質は、手法やソリューションを先に考えるのではなく、人の痛みを理解することにあります。これがイノベーションの源泉で、マーケティングからセールス、商品開発まで全てに影響するのです。
また、多様な視点と意思決定スタイルを持つチームが非常に重要です!これからチーム構成を見直していきたいと思います。
このブートキャンプは、思考法だけでなく自己理解も深まる貴重な経験でした。皆さんも機会があればぜひ参加してみてください!ご質問があればいつでもお聞きください。
デザインシンキングは方法論を超えた、人間中心のイノベーション哲学です。