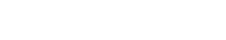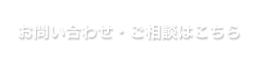A2(Aichi-Austin)Innovation Kick-start Program に参加してのまとめ
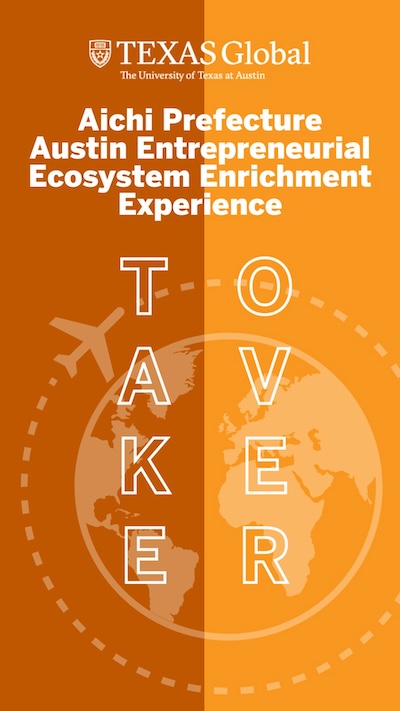
この1週間愛知県さんと、同行した起業家3名と、愛知県の事業を受託しているトーマツの方2名と共に、A2(Aichi-Austin)Innovation Kick-start Program(米国テキサス州への起業家派遣プログラム)に参加していた。
色々思うところがあり、まとめてみたいと思う。
ストーリーを語る能力がヘボい

海外VC向けや、Q-Branchという場所でピッチをさせて頂く機会を得たが、正直手応えもなにもなかった。
自分の場合、ストーリーという言葉を聞いて思いつくのは、桃太郎である。
起承転結があることは良い。
問題1:ヒーローコンプレックス
しかし問題は自社をヒーローにしてしまいそうになるところだ。
ヒーローは顧客であり、我々やプロダクトは、所謂ダンブルドアやオビワンの役割を担うべきだ。
Capital factoryで出会った、セールス系のSaaS企業は彼らのことを、”フットボールのコーチの様なもの”だと表現していた。
問題2:技術特異性コンプレックス
ライト兄弟しかり、エジソンしかり、スティーブ・ジョブズしかり、彼らは世界初の技術を開発したわけではない。世界でもっともそれらの技術をアダプティブに活かしたことが彼らが起こしたイノベーションである。
日本にいると、”技術”で語りたくなってしまうが、技術によってどんな効能をもたらせるのかという点に絞ってストーリーは作らなくてはならない。
問題3:うんちく長い問題
ストーリーはシンプルで、わかりやすくなければいけない。
人々はベストプロダクトを買うわけではなく、最も理解しやすく商品を買っている。
ストーリーには出てこない、裏側の設定について考え抜いたとしても、全てをストーリーに網羅する必要はない。
商品効能は「CV率を増加させる」くらいシンプルで良い。
問題4:Why Why Why 問題
とにかくWhy, I believe といった根源に関わることをストーリーでは語るべきだ。
HowやWhatばかり喋っても誰も覚えちゃくれない。
問題5:VCに向けて、現在と未来のドットをコネクトできていない
実際ほとんどの国内SaaS企業がそうであるように、我々もBPaaS(BPO * SaaS)というモデルで現在お客様に向き合っている。システムで補完できないところを、人間がサポートすることで、お客様に効能を提供。効能を提供できるということは経済価値が発生するので、投資資金にだけたよることなく、ブートストラップな成長を実現することができる。
ところが、いざVCを前にすると、その形式について、日和ってしまうことがある。
- 「アナログな部分があるから労働集約的なボトルネックがあるんですよね…」
- 「投資資金も基本的には比例で伸ばす形です…」
といった具合だ。
しかし大事なのは、現在と未来を”コネクティング・ザ・ドット“することである。
市場に既に受け入れられて効能を発揮していることはむしろ誇るべきことで、調達資金によって、アナログ部分をAIやシステムに徐々に置き換えることで、ボトルネックを解消したいといったストーリーにすべきだ。
アナログなサービスで効能を発揮し、ブートストラップな成長を実現させる。更にボトルネックを解消し、成長を加速させる為に、資金を調達するということ自体は、戦略だと言い切るくらいで良い。
問題6:サプライ側のメッセージ問題
これは、同行している起業家に指摘されたのだが、現状の「情報洪水に溺れる人類をAIとソフトウェアで助ける」はユーザー側のメッセージなので、サプライ側のメッセージ(=ToB向けのメッセージ)があった方が良いよね。という指摘を受ける。確かに、現在のビジョンは将来を見越して抽象度をかなり上げたものであり、現実に即したプロダクトのストーリーにも同様のものが必要である。
例:マーケティング担当者のアイディアを全てカタチにする
問題7:プロダクトロードマップ問題
「将来こんな機能を開発します。何故ならば…」という、説明が出来るようになる必要がある。
現状はもっと行き当たりばったりな感じであるからだ。
- 既にアダプティブであるもの
- ニーズがあるが、現状の市場製品では十分対応できていない
それらをシステム化・AI化しますという文脈だ。
プロダクトロードマップを元に、投資家には語りたいと思う。
悔しいかな、海外VCからは正直相手にされていない

James Bond from Japanと言った際のリアクション
我が社がということだが(もっとも自身の問題であって、この場にいたのがEwdisonであったらリアクションは違っただろう)、マーケティングという世界屈指のコンペティティブな市場で、日本の会社がノコノコやってきて「何するの?」という感じなのだろう。
もちろん、彼らはエコシステムの一員という立場で、コミュニティサービスとしてアドバイスをくれたり、質問に答えたりしてくれているが、新しい投資先としてお眼鏡にかなった手応えは全くない。
国内でシェアを持っているサービスを米国に持っていくような文脈や、日本のグローバル企業の米国支社などにサービス提供を行うことで、実績を作って置くことが重要である(という様なフィードバックを受ける)。そもそも市場が変われば、ニーズや最適化などのGo To Marketはかなり違うのでは?という指摘も受けた。
米国

物価もさることながら、市場、人材、キャピタルの集まり方がエグい。
遠隔地に居てどうこうなる気がしないので、いずれ進出しなければいけないと感じた。
その他
- Dellの本社で見た、AIカメラのユースケースがかなり面白かった
- ヘルスケアなど命に関わる領域の製品のエクスキューズが面白かった
以上精進せねばと思い候。
新しいストーリー案
株式会社APOLLO11はロケットを作っている会社ではなく、マーケティングのソフトウェアを提供している所謂SaaS企業です。
私はマーケティングの話をするのが好きです。マーケティングとは突き詰めると「人は何を考えるか」というテーマに行き着くからです。私は純文学が好きですが、仕事の中で「人間とは」というテーマを突き詰められるのは、マーケティングくらいかなと思うんですね。
そういった話を、マーケティング担当の方とすることも大好きです。「何もたさない。何もひかない」という昔のサントリー山崎のキャッチコピーを教えてもらうこともありましたし、居酒屋に連れてかれて、「よっしー、最も焼酎らしいのはどのラベルデザインだ?」とか聞かれたりですね。
マーケティングの本質は、データよりも、こういった「何が人の心に刺さって、何が行動を起こさせるのか」という点にあると信じています。
私は確信していますが、マーケティング担当者が「やりたい!」と思ったことを全て実行することが出来れば、間違いなく前年比10%20%の成長が可能です。でも現実はそういきません。
マーケティング担当者には3つの問題があるからです。
(1)エビデンス
まず「やりたい!」と思っても、企業として動いているわけで、チームや上司を説得しなければいけません。
その為のエビデンス集めに時間を取られることもあれば、そもそも直感に起因している為、エビデンスがないことの方が多いのです。
(2)予算
「やりたい!」と思っても、実行には予算が掛かります。上手くいくかどうかわからないものに、予算を取り付けることは大変ですし、何でもかんでもやれません。
(3)多忙
エビデンスや予算取りだけでも大変な仕事ですが、いざ実行するとなると、デザインを起こしたり、システム部門に実装を依頼したりと、舵取りだけでもかなりの業務負荷となります。マーケティング担当者は実際多忙なので、手が付けられていない仕事を山の様に抱えています。
この問題をAPOLLO11が解決します。我々は提供するAPOLLO OptimizeというABテストツールとAPOLLO ModelingというBPOサービスによって、マーケティング担当者のアイディアを全てカタチにします。
具体的なソリューションの話をします。
アクセス数 × CV率 = CV
私たちのサービスはCV率を向上させるものです。
具体的には〜(提供するものによって、エビデンス・予算・多忙を解決するストーリーを)