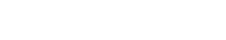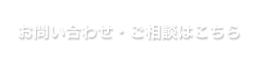読書感想文「星を継ぐもの」ジェイムズ・P・ホーガン(1977)
「SF小説不朽の名作として著名でかつ面白い」と紹介され、拝読する。
月面で発見された、宇宙服をまとった人間の遺体が死後5万年は経っているという発見から物語は始まる。
SFでありながら、謎解きミステリーである。
また、主人公のハント、彼の上司になるコールドウェル、ライバル役のダンチェッカーのキャラクターを際立たせることにより、小説らしい面白さが作品に与えられていた。
とりとめなく、感想を。
「無限エネルギーの獲得が人類の争いを消失させる」について
放射能汚染の心配がない、”きれいな核爆弾”が開発されたという描写に続く文を抜粋。
歴史上この一時期を通じて、二十世紀の置き土産だったイデオロギーや民族主義に根ざす緊張は、科学技術の進歩によってもたらされた、全世界的な豊穣と出生率の低下によって霧消した。古来歴史を揺るがせていた対立と不信は民族、国家、党派、信教等が婚前と融和して巨大な、均一な地球社会が形成されるにつれて影をひそめた。すでにその生命を失って久しい政治家の理不尽な領土意識は自然に消滅し、国民国家が成熟期に達すると、超大国の防衛予算は年々大幅に削減された。
国民国家は、戦争をする為のフレームであり、多くの戦争の目的が資源の獲得であることから、「無限のエネルギー資源を得た人類から争いがなくなる」という仮説?皮肉である。
さてどうであろうか。ライフラインに何の心配もいらない、ある100人の村があったとて、人間が人間である以上、争いがなくなるイメージはない。
更に、小説公開から約50年。国民国家は成熟どころか、衰退しているように感じられる。例えば日本において、国家という共同体の為に自発的に行動している人がどれだけいるのだろうか。無論、納税などの義務は果たすとして。
「サピエンス全史」で有名なユヴァル・ノア・ハラリは、飢餓・戦争・疫病を克服した人類は、ホモ・デウス(神)に昇華するという論説を展開した。
現代において、飢餓は政治問題であり、飢死者の3倍も糖尿病の死者がいる現状について言及した。また、戦争によって土地を収奪するよりも、サイバー空間で富を独占することの優先度が高く、医学の発展で疫病は克服したと述べた。
※論説を発表したあとにCOVIT-19は発生する。
しかし昨今のウクライナ戦争を始め、ガザの紛争は、その目的を「資源獲得」で一括りにすることはできない。むしろ世界中でイデオロギーや民族主義が伸長しているように感じられる。これは無限のエネルギーを得たとしても解決しないと思われる。
未来予測の難しさ「たばこ」
会議室で、灰皿いっぱいのタバコの吸い殻がよく描写されていた。
しかし、2025年現在、そうした光景はオフィスから消失してしまった。
投射機で会議室にスライドを投影する光景も懐かしく思われた。
物語に厚みをもたせるライバル構造
ダンチェッカー学会における輝かしい業績は当代屈指であることも知らないわけではなかった。おまけに、目下の議論についてはハントは門外漢だった。教授に対するハントの嫌悪は別のところにあった。ハントはそれをあるがままの事実と受け取り、いたずらに理屈を付けて自分の気持ちを騙すつもりはなかった。要するに、ダンチェッカーの何もかもが気に入らないのだ。ダンチェッカーは痩せすぎている。着ている服はあまりにも古めかしい。その服をダンチェッカーは、まるで洗濯物を干しでもするようにまとっている。時代遅れな金縁眼鏡は笑止千万だ。もったいぶった丁寧な話し方は不愉快である。彼ははたして、生まれてこのかた笑ったことが一度でもあるのだろうか。
ダンチェッカーの”嫌な奴”具合は巧みに表現され、主人公のライバル役として物語に花を添える。
途中主人公と邂逅しながらも、最後は彼の科学者としての頑強さが物語を最終的な局面に連れていく。
英国ジョークの構造について
UNSAのコマーシャルを聞かせるためにわたしを呼び出したわけじゃあないだろう
主人公はイギリス人として、しばしばこういったジョークを披露する。
英国的なジョークの構造は、会話や状況を構造的(文脈的)に捉えた上で、構造に対して、抽象化する、ズラす、逆を言うなど加工する。そして、その加工のやり方が意地悪(皮肉混じり)なのである。
英国ジョークが言いたければ、”頭の良い嫌なやつ”を演じようとすれば良い。
記憶を呼び覚ますこと
地球の緑の山河も、紺碧の空も、もはや彼らの生存にとって必要な条件ではなかった。それらは、ただ、かつては現実に思えた夢の名残として、ある種の鮮明な記憶を呼び覚ますものでしかなかった。
この表現から想起されたことを書く。呼び覚ませる記憶がない奴は、それらを抽象化して取り出すこともできない。以前歴史を学ぶことは、自分が何者であるかを知るために重要だということを書いたことがある。しかし、もっと切実な問題として、歴史を学ばなければ(この小説で言えばミネルヴァから学ばなければ)、自分の人生を幸せにしてくれるかもしれない価値観や、考え方や方法を生涯得ることができない。
ついつい、新しい情報に価値を感じてしまうが、人間の脳の構造が100万年前からほぼ変わっていないことを考えると、例え古かろうと、自分より遥かに優秀な人が残したものには価値がきっとある。
天才同士を共闘させる為に
コールドウェルは、ハントとダンチェッカーという、対立する天才同士を木星の衛星ガニメデに派遣することで融和させ、共闘させた。
経営に話は飛躍するが、本社で悠々自適に仕事をさせるよりも、前線の支店や営業所でチームを組むことで結束や責任感のあるリーダーが生まれることは想像ができる。
コリエルのネアンデルタール人説で話は終わる
エンディングでさらなる謎が残された。
きみは、あの眉のあたりの隆起に気がついたかね?
これはネアンデルタール人含め、旧人の特徴である。
- えっ、コリエルはネアンデルタール人なの?
- えっ、じゃあネアンデルタール人も、ルナリアン由来なの???
- じゃあ誰がネアンデルタール人を絶滅させたの???
コリエルの人間離れした体力や、体格に説得力を持たせる謎を残して本編は終わる。
いやぁ面白かった。